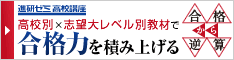テストは、暗記が不可欠 繰り返し反復で記憶を定着させる
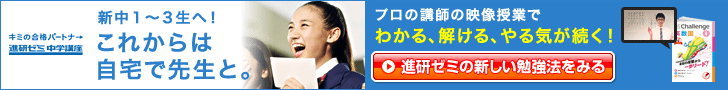
中学1年生 音楽のテスト勉強法

中学では、「中間テスト」「期末テスト」「実力テスト」が 行われます。中間テスト 実力テストは、国語 数学 理科 社会 英語の主要5教科、期末テストでは、「実技4教科」のテストが行われます。実技4教科とは?、「音楽」「美術」「技術・家庭」「保健体育」のことです。
期末テストの実技4教科は、高校入試の調査書(内申書)にも 影響をもたたすので 軽視してはいけません。
まず テスト範囲が発表されたら 教科書を開き 楽曲の作曲者と作詞者。外国の歌や曲は、作曲者が生まれた国も把握しておきます。歌詞や記号も暗記します。学校によっては、校歌の問題が出ることも・・。

中学では、アルトリコーダーを 吹きますが 指づかいの問題も出題されます。
高い音を出すとき 裏穴に わずかな スキマを作るサミング、
演奏を止めたり出したりする舌の動きタンギング
以下に出題されやすい傾向を 箇条書きにしてみました。教科書と照らし合わせ テスト勉強の参考にしてください。
中学の期末テスト (音楽)で出題されやすい問題
- 音楽著作権
- 作曲者について(生まれた国も)
- 作曲された時代
- 作曲された 背景・・(とくにエピソードがあるクラッシック曲など)
- 協奏曲(コンチェルト)と 交響曲(シンフォニー)の違い
- 作曲者・作詞者について(日本の歌)
- 演奏形態(ソプラノ、アルト、テノール、バス
- 楽曲について
- 歌詞の意味について・・(古い日本の歌の場合)
- 歌詞の穴埋め
- 日本の楽器の特徴
- 日本の伝統芸能 雅楽について (笙=しょう)、(竜笛=りゅうてき)、(琵琶=びわ)、(箏=そう)→(楽箏=がくそう)、太鼓(楽太鼓 釣太鼓)、(鞨鼓=かっこ)(篳篥=ひちりき)
- 世界の民族音楽
- ア・カペラについて
- だんだん速く 少し 遅くしていく などの 記号
- 郷土の芸能、長崎くんち(長崎県) さんさ踊り(岩手県) 神田祭(東京都)天神祭(大阪府) 阿波踊り(徳島県) エイサー(沖縄県) 秩父夜祭(埼玉県) 祇園祭り(京都府) これらの県
音楽のテストで 出題されやすい 記号

記号は、英語で 書けなくても 大丈夫ですが 読めるようにしておきましょう。良く出るのは、強弱記号、速度記号、などの音楽記号です。シャー^プ フラット、フェルマート、タイ、アテンポ(元の速さで)など用語(記号)の読み方 意味を 覚えておきましょう。
| フェルマーター | 音符 休符を ほどよくのばすこと |
|---|---|
| レガート | legato 音と音の間に切れを感じさせず、滑らかに続けて演奏する方法 |
| スタッカート | staccato 一音符ずつ切り離して歯切れよく演奏すること、また歌うこと |
| リタルタンド | ritardando .rit 、テンポを次第に落としてゆく |
| アッチェレランド | accel. テンポを次第に速めること |
| グランディオー | 壮大に、堂々と grandioso |
| アレグロ | allegro 陽気に |
| モデラート | Moderato 中くらいの速さで 中庸な速度で |
| フォルテ | 強く |
| メゾフォルテ | 少し強く |
| ピアノ | 弱く |
| メゾピアノ | 少し弱く |
| デクレシェンド | だんだん 弱く |
| フラット | 半音下げる |
出題されやすい日本の歌 楽曲名

以下の日本の楽曲は、出題される可能性が 高いです。文部省の新指導要領の中で 歌唱教材について以下の楽曲を推奨していたからです。 季節的に 1学期は、花 早春賦、2学期は、赤とんぼ 浜辺の歌 夏の思い出 3学期は、荒城の月 花の街??
- 「赤とんぼ」 三木露風(みきろふう)作詞 山田耕筰(やまだこうさく)作曲
- 「荒城の月」 土井晩翠(どいばんすい)作詞 滝廉太郎(たきれんたろう)作曲
- 「早春賦」 吉丸一昌(よしまるかずまさ)作詞 中田章(なかだあきら)作曲
- 「夏の思い出」 江間章子(えましょうこ)作詞 中田喜直(なかだよしなお)作曲
- 「花」 武島羽衣(たけしまはごろも)作詞 滝廉太郎作曲
- 「花の街」 江間章子作詞 團伊玖磨(だんいくま)作曲
- 「浜辺の歌」 林古溪(はやしこけい)作詞 成田為三(なりたためぞう)作曲
1年生の教科書に 掲載されている楽曲が 中心になりますが、以上の 曲は、Youtube 動画 で聞いたり 授業で 習ったなら 出題されると 思って 間違いありません。
発声 合唱のポイント

普段から 合唱のときは、必要以上に 口を大きくあけて 表情豊かに 歌うようにします。自分からは、指揮者1人 先生 一人しか 見えないけれど 先生は、全体を通して キミを評価していることを お忘れなく!まっすぐ立ち 大きな声で 目を開き 感情(情感)をこめて 歌う・・歌うときは、しっかり のばす部分は、よく のばす、音楽の記号も 習ったものは、覚えておきます。
テストで 出題されるとしたら、背筋を伸ばして歌う、足を軽く開く、肩の力を抜いて歌う、口を大きく広げて 歌う、目線は、やや上に向ける。重心を少し前に、リズムやハーモニーを 大切にする など 合唱の際 気を付けなければならないポイントが 出題されます。